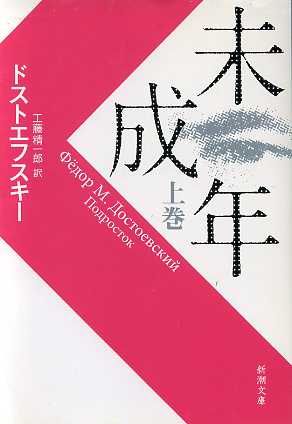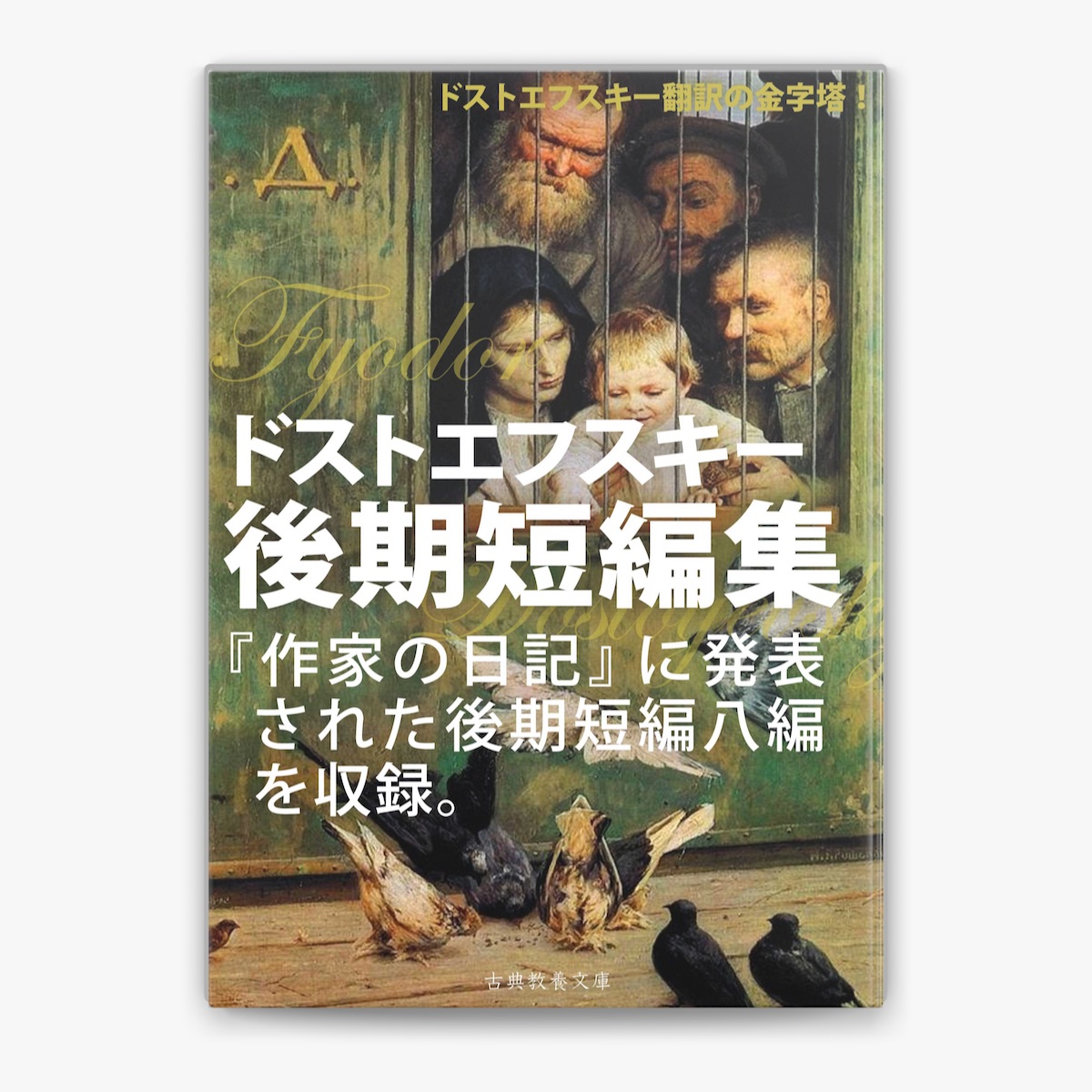| |
[709] 2024/12/23/(Mon)17:45:58
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (13) |
| 本文 |
『罠(わな)』
←『鰐(わに)』
(『地下室の手記』を発表した年の翌年の
65年3月にドストエフスキー編集の雑誌
「世紀」に発表された中編小説。
店の見世物だった鰐(わに)に夫が呑(の)
まれて夫が鰐の中から世間批評をつぶや
く騒動を描いている。)
矢庭(やにわ)に相手に罠(わな)にはめられた男が続いて逆に相手を罠にはめ、引き続いてまた相互に罠にはめられ続けるという飲み込みの遅い人を食った多弁の男達の物語。
(語注: ・矢庭に=いきなり。)

|
| |
|
| |
[708] 2024/12/21/(Sat)09:24:43
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (12) |
| 本文 |
『ネットにチカラをいれ
て寝ずにいるのはよくないわ』
←『ネートチカ・ネズワーノワ』
(『貧しき人びと』を発表した年(46年)
の6月に起稿し49年1月・2月・5月に
「祖国雑誌」に発表されたが、同年4月
以降のドストエフスキーの逮捕・収監
・流刑によって続きの発表は中断され、
その後も完成に至らず、未完の小説と
なった。
若い女性「わたし(ネートチカ)」が自
分の少女時代のことを回想して語る長
編小説。
ネットの昔懐かしい曲の映像の鑑賞にふけって夜更かしを続ける若い後家(ごけ)有閑マダムが昼寝とレズばかりして健康を壊す物語。
|
| |
|
| |
[707] 2024/12/18/(Wed)17:43:12
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
マカール老人の教え・考え |
| 本文 |
『未成年』のマカール老人が作中で述べている教え・考えとして、次の1〜6を挙げたい。
1、人のあり方として、陽気であること、笑うことをすすめている。
2、人のあり方として、端麗さ(品位)を説いた。
3、「キリストさまがおっしゃっておられるのは、そんなことじゃない。『行きて、汝(なんじ)の富をわかちあたえよ、そして万人の僕(しもべ)となれ』 こうおしゃっておられる。それでこそ今までよりも百万倍も豊かになるのだよ。だって人間というものは、食物や、高価な衣装や、誇りや、羨望(せんぼう)で幸福になるのではない、限りなくひろがる愛によって幸福になるからだよ。そうなれば十万や百万ぽっちの少しばかりの財産ではなく、世界中を自分のものにすることになるのだ!」と述べて、愛を重視し、人は愛(限りなくひろがる愛)によって幸福になり、多くのものを手に入れることができると説いた。
4、「神のない生活は苦しみでしかない」と言って、神への信仰が生きていくことの支えになることを述べた。
5、「お祈りはいいものだよ。心がさわやかになる、眠るまえにも、朝起きたときも、夜中にふっと目がさめたときも。」と述べて、朝夕、祈ることをすすめている。
6、「自殺は人間のいちばん大きな罪だよ」と述べている。
以上は、いずれも良き教えだ。晩年におけるドスト氏自身の思い・考えでもあったと思う。
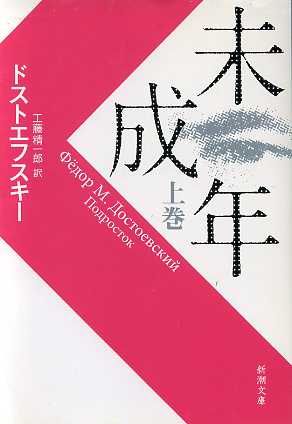
|
| |
|
| |
[706] 2024/12/16/(Mon)17:34:55
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (11) |
| 本文 |
『プロだと見栄を張るちんけな紳士』
←『プロハルチン氏』
(『貧しき人びと』発表の翌年の46年10月に
「祖国雑誌」に発表された短編。
徹底的に倹約してペテルブルグの下宿で
貧窮生活を送るプロハルチン(中年の独り
身の下級官吏)の生活ぶりを描いている。)
表向きは倹約のプロだと見栄を張っていた紳士が実は陰で贅沢をしていたことが死後皆にわかってしまうちんけな男の物語。
(語注: ・ちんけな=スケールの小さい小者(こもの)の。)
|
| |
|
| |
[705] 2024/12/14/(Sat)10:11:30
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (10) |
| 本文 |
『ポールでズッこける夫人』
←『ポルズンコフ』
(シベリア流刑になる前年の48年2月
に「祖国雑誌」に発表された短編。
社交界で道化を演じているポルズン
コフが上司との間の過去の失敗談を
語る話。)
日常生活や家庭で失敗やミスばかりしていて、そのたびに後退(あとずさ)りして、工事現場に立ててあったポールや転がっていたゴルフボールに触(ふ)れてはズッこけてばかりいるヘマでドジな夫人の物語。なお、彼女は曲「So Bad」を歌うポール・マッカトニーや曲「ズンドコ節」を歌う氷川きよしの大ファンでもあった。
|
| |
|
| |
[704] 2024/12/11/(Wed)18:44:55
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の特徴 (16) ― 寄り添う人物を配していること |
| 本文 |
※追記更新 24/12/15 18:00
ドスト氏の小説の特徴として、主人公や登場人物に、友人や看護婦のように寄り添う女性・男性がしばしば配(はい)されているということが言えると思う。
『罪と罰』では、
・ラスコーリニコフに好人物のラズミーヒン
・ラスコーリニコフにソーニャ
『白痴』では、
・ムイシュキン公爵とラゴージン
・ナスターシャ‐フィリポヴナにムイシュキン公爵
『悪霊』では、
・キリーロフとシャートフ
・スタヴローギンにダーシャ
・リーザにいつも付き添っている婚約者マヴリーキー
・ステパン氏にワルワーラ夫人
・ステパン氏にソフィア・マトヴェーエヴナ(侍女)
・シャートフとマリー(元妻)
『未成年』では、
・アルカージーと妹のリーザ
・アルカージーにワーシン
・ヴェルシーロフにソーフィア
『カラマーゾフの兄弟』では、
・アリョーシャにラキーチン
・アリョーシャにリーズ
・ドミートリイにグルーシェンカ
・イヴァンにカチェリーナ
・スメルジャコフにマリヤ
『貧しき人びと』では、
・マカール・ジェーヴシキンと少女ワーレンカ
『虐げられた人びと』では、
・ナターシャにイワン(語り手の私)
『百姓マレイ』では、
・9歳の私に農夫マレイ
『白夜』では、
・ナースチェンカに私
『死の家の記録』では、
監獄の敷地内の野良犬に私(ゴリャンチコフ)
といった具合だ。
ドスト氏は、登場人物に寄り添う友人や男性・女性を設けることで、小説に感興を添えるに終わらず、その登場人物の救い・信頼・慰労の道の可能性を示そうとしたのだと思う。
人には寄り添って看護し慰めてくれる人がいることが大切だというドスト氏の人間観や優しさも現れていると言えるだろう。

[リーザにいつも付き従っているマヴリーキー。
ロシアのテレビドラマ「悪霊」より。]
※
ドストエフスキーの小説の特徴(1〜15)
|
| |
|
| |
[703] 2024/12/09/(Mon)17:32:19
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (9) |
| 本文 |
『掃除機で遊ぼうとするな』
←『正直な泥棒』
(シベリア流刑になる前年の48年4月に
「祖国雑誌」に発表された短編小説。
恩人に対して盗みをしたことを亡く
なる時に正直に述べたという話。)
長くで広い廊下を掃除するに掃除機とフローリングモップで遊び過ぎてツルツルにしてしまい、浮かれて調子に乗って途中でうっかり思いっきり滑(すべ)って半回転してしまって、頭の打ちどころが悪くて、過去の記憶も喪失してしまい、以前細君のへそくりの一部をこっそり盗んだことがあったことを最期に細君に謝罪できずにその日に亡くなってしまった男の話。
|
| |
|
| |
[702] 2024/12/07/(Sat)08:55:44
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (8) |
| 本文 |
『まごついた白菜の老婆』
←『百歳の老婆』
(76年3月の「作家の日記」に掲載され
た短編小説。たどりついた孫の家で
104歳の老婆が突然死してしまう話。)
白菜が大好物の白髪の一人住まいの老婆が、噂の白菜を求めて遠出を敢行するが、帰り道で、買い占めた白菜を抱えて、もてあまし、迷子になって、まごついてしまい、哀れにも客死(かくし)してしまうという話。
白菜の/かがやく量を/もてあます
〔文挟 夫佐恵(ふばさみふさえ。百歳で
病没の女性俳人)の句〕
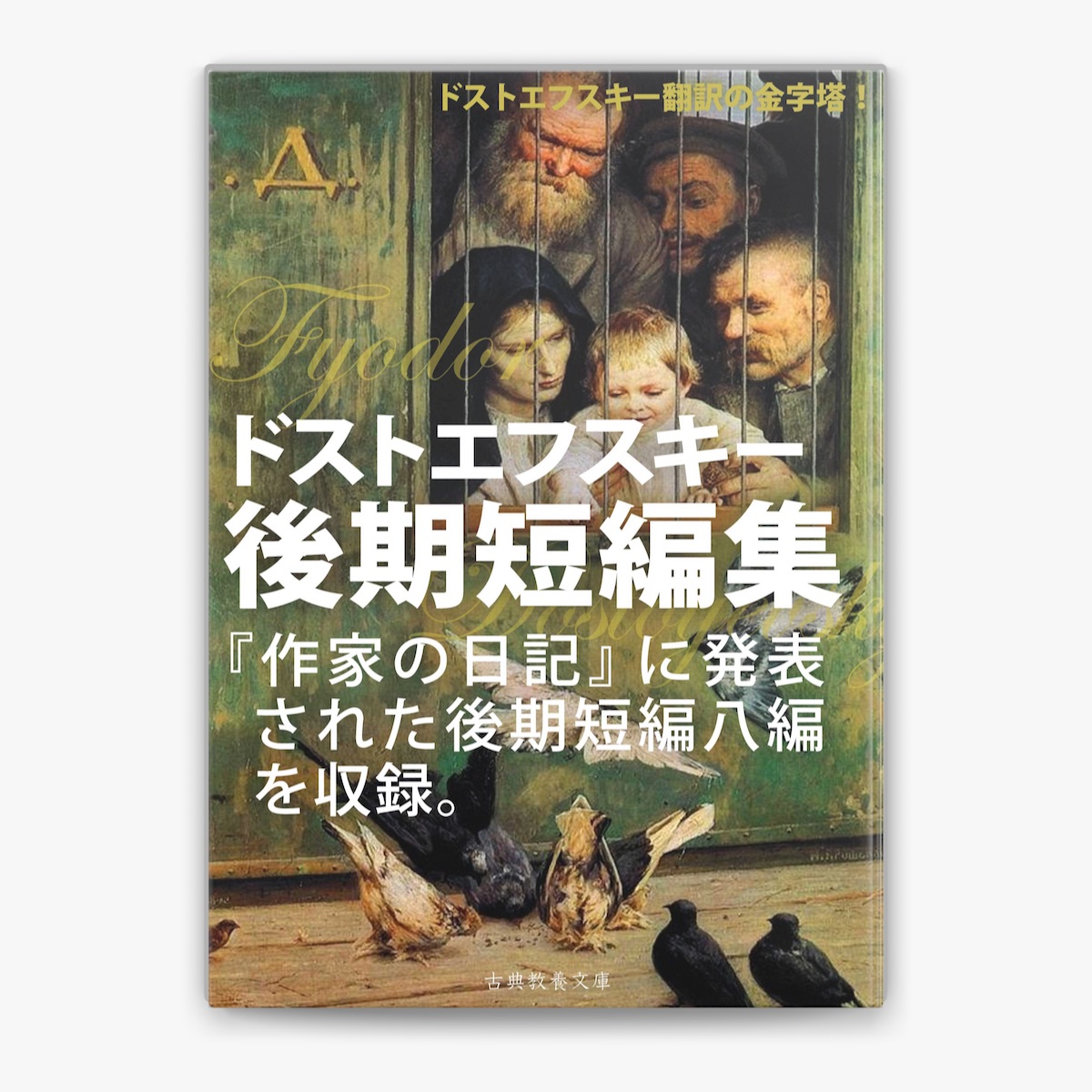
|
| |
|
| |
[701] 2024/12/04/(Wed)18:04:24
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの言葉(34) ― 意識し考え過ぎることの弊害とその克服の道のこと |
| 本文 |
※追記更新 24/12/04 18:50
賢い人間が本気で何者かになることなどできはしない。何かになれるのは馬鹿だけだ。
(『地下室の手記』より。)
あまりに意識しすぎるのは、病気である。正真正銘の完全な病気である。人間、日常の生活のためには、世人一般のありふれた意識だけでも、充分すぎるくらいなのだ。
(『地下室の手記』より。)
上の言葉は、『地下室の手記』で述べようとした人間の有りようについてのドスト氏の思いや考えの基調をよく示している言葉だと思う。
つまり、自分のことについてあまりにあれやこれやと意識し考え過ぎることは、既存の自己のことの否定排除や分裂や行動の停滞をもたらし、その調子でそのあとに新たな自己を作り上げていくことや行動ができずにいると、自分の有りようや性格や行動の傾向・一貫性を減じてしまうことになる。
一方、意識し考えることをしなければ、人は、既成のその堅固な習慣と行動基準にしたがって、日々、考えや行動が馬鹿なものであったり誤っていたりしていても、迷うこと疑うことなくストレートに生きていく。
ドスト氏は人のこの二方向性について生涯思いを巡らした。前者が大切だとしながらも前者がうまくいかないこと(何かになっていけないこと)にずっとこだわり、後者の人を馬鹿だと言いながらも、後者の有りように一種の憧れを持ち続けた。
『カラ兄弟』において直情径行の行動の青年・ドミートリイを登場させたのは、後者の人の有りようについての良い意味での積極的な思いがもとになっているように思う。
また、自己の分裂化・霧散化といった前者の問題は、小林秀雄氏やアンドレ・ジイド氏などが洞察し指摘したように、神・キリストへの信仰、そして、文学の創作に打ちこむという次元を導入することで、解決・解消に向かっていったと言えるのかもしれない。[ 1、2 ]
|
| |
|
| |
[700] 2024/12/02/(Mon)17:41:04
| 名前 |
Seigo
|
タイトル |
ドストエフスキーの小説の題名をパロる! (7) |
| 本文 |
※追記更新 24/12/03 07:32
『千こく』
←『宣告』
( 76年10月の「作家の日記」に掲載さ
れた小品。ある男が自殺の前に意識
することによる苦痛と虚無感を人間
に与えた「自然」を糺弾した独白体
の作品。)
キリの無い独白の作品は勘弁願いたい、全体で1000文字の作品にしてくれと雑誌編集部に頼まれて、きっちり千文字にして、ある男が意識というものを人間に与えた「自然」に対する感謝をこいた小品。せんでもいい毒を吐(は)くことや自殺の念のない独白の佳品になっている。
(語注:・こく=述べる。)
※
ドストエフスキーの小説の題名をパロる!(1〜6)

小品『宣告』を今回、米川正夫訳の上の『ドストエフスキイ後期短篇集』であらためて読んでみた。文庫本でほんの6ページの小品。『白痴』での青年イポリートの告白の二番煎じのような文章だが、ドスト氏が、人間に意識が与えられていることをめぐる問題、意識することは病気であるというテーマ、私たちのこの世界の意味のことにずっとこだわっていたことが窺(うかが)われる。
|
| |
|