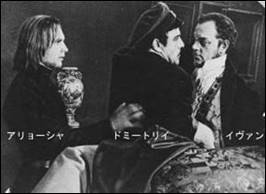| |
[808] 2025/12/15/(Mon)17:36:01
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�w�n�����̎�L�x�̂��� |
| �{�� |
�����ƌ������������ƂƂ��ĈȑO���狓���Ă����A
�@�w�n�����̎�L�x�̓h�X�g�G�t�X�L�[�̏�����
�@ �n��ɂ����āA�ǂ��������_�ŗv(���Ȃ�)�Ƃ�
�@ �鏬���Ȃ̂�
�Ƃ������Ƃ��A���̂��сA�����̋C�t��������ɓY���āA���t�[�m�b�܂Őq�˂Ă݂��B
�@�@�@���@���̎���Ɖ́A������
���e�ʂ����łȂ��A�ǂ��������o��l�����ǂ��`���Ă������Ƃ����ʂł��V�@����ł��o������i���A�Ȃǂ�AI����̎w�E�́A�Q�l�ɂȂ����Ǝv���B
����̎�������āA���������炽�߂Č������Ă݂����Ƃ́A����ŏ����G��Ă���ʂ�A�w�n�����̎�L�x�̎�l���̒j�̎��ӎ��ߏ�ŁA����������A�����������Ă��Ȃ���A���̕ǂ���̑ŊJ�����߂Ă���Ƃ����l�����Ə́A�w�߂Ɣ��x�͌����܂ł��Ȃ��A���̌�̒��ҏ����Q�̏o���_�ƂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B
�w�߂Ɣ��x�ł���A��l���̒j�ƃ��[�U�́A���X�R�[���j�R�t�ƃ\�[�j���ւƈ����p����Ă���B�w�n�����̎�L�x�Ƃ�����i�́A��l���̒j�̂悤�Ȑl�����A��ɁA�ǂ̑ŊJ����A�Љ�ւƂ����o�āA�����ɐ����Ă������A�Ƃ����W�J��\�����Ă��āA�h�X�g�G�t�X�L�[�͂��̌�̏����ŁA�����I���ؓI�ɂ��̍s���̔ߌ��ƍX����`���Ă������ƂɂȂ�B
�h�X�g�G�t�X�L�[�ɂƂ��Ắw�n�����̎�L�x�̈Ӌ`�ɂ��ẮA������A����Ɍ����������Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[807] 2025/12/10/(Wed)22:08:03
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�w�s����ꂽ�l�тƁx�̌���̂��� |
| �{�� |
�@�@���NjL�X�V 25/12/11 18:20
���V�A��̕������˂āA�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����̌�����m�F���Ă�����A�w�s����ꂽ�l�тƁx�̌���ƖM��̑�ɂ��āA�킩�������Ƃ��A����������܂����B
�w�s����ꂽ�l�тƁx�̌���ł���A
�@�@�T�~�y�w�u�~�~���u �y �����{�����q�|�u�~�~���u
�����āA�܂��A�H�H�H�@�Ǝv�����̂ł����B
(�e�����̃��V�A��̌���́A���ׂāA�y�[�W���̃R�[�i�[�u�e�����A����̈ē��v�ɈȑO����t���Ă��܂����A�܂��܂��ƌ����̂͂��̂��т����߂ĂŁA�w�s����ꂽ�l�тƁx�̌�������āA�M��́u�s����ꂽ�l�тƁv�Ȃ̂ɁA�w�߂Ɣ��x�̑�̂悤�ɁA�uA��B�v�́u�Ɓv�̈Ӗ��̐ڑ����u�y(�C�[)�v����(�͂�)��ŁA��̌�傪����I�H�Ƃ������ƂŁA�H�H�H�ƂȂ��Ă��܂����̂ł����B)
�����ŁA�m�F���Ă݂��Ƃ���A��̌���́A���̂܂ܖA�u�ڂ��߂��A���J���ꂽ�v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�A�����̖M��̑薼�Ƃ��ẮA����ł͏璷�ɂȂ�̂ŁA��̌`�e�������Ŗāu�s����ꂽ�v�Ɩ��Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�Ȃ��A���V�A��ł͌`�e���͕����`�̌`�ɂ��邱�ƂŁu���̂悤�Ȑl�X�v�̈Ӗ������̂ŁA����ł́A���̂��Ƃ́u�l�X(�|���t�y �����[�W)�v�͏Ȃ��Ă��܂��B
(���Ȃ݂ɁA�����w�n�����l�тƁx�̃^�C�g���́A�����ł́A
�@�@�A�u�t�~���u(���n����) �|���t�y
�ƂȂ��Ă��āA�|���t�y��t���Ă���B)
����́A�w�s����ꂽ�l�тƁx�̌���̕\���A�y�сA���V�A��ɂ��Ă��낢��Ƃ킩���ċ����[�������ł��B
�ȏ�̂��Ƃɂ��āA���̂��т��A���t�[�m�b�܂Ŗ₤�Ă݂܂����B
�@���@����Ɖ�
�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@
�@[�w�s����ꂽ�l�тƁx�̌���]
�@�@�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[806] 2025/12/06/(Sat)19:16:11
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�h�X�g�G�t�X�L�[�ܑ̌咷�ҏ����̖|��̂��� |
| �{�� |
�h�X�g�G�t�X�L�[�ܑ̌咷�ҏ����̂��ׂĂ�|�Ă���Đ쐳�v���A�������F���A�T�R��v���̂ق��ɁA�ܑ咷�ҏ����̂����A���ȏ�A���Ă��邨���Ƃ��̏������A�ȉ��̒ʂ�A�m�F���Ă݂��B
�k�_�M�s�@�@ �w�߂Ɣ��x�w���s�x�w�����N�x
�@�@�@�@�@�@ �w�J���}�[�]�t�̌Z��x
�� �v��Y�@�@�w�߂Ɣ��x�w����x
�@�@�@�@�@�@ �w�J���}�[�]�t�̌Z��x
�]�� ��@�@�@�w�߂Ɣ��x�w����x
�@�@�@�@�@�@ �w�J���}�[�]�t�̌Z��x
�r�c �����Y�@�w�߂Ɣ��x�w����x
�@�@�@�@�@�@ �w�J���}�[�]�t�̌Z��x
�X�c�����@�@ �w����x�w�J���}�[�]�t�̌Z��x
�������t�@�@ �w�߂Ɣ��x�w���s�x
���R �ȎO�Y�@�w���s�x�w�J���}�[�]�t�̌Z��x
�H�� ����Y�@�w�߂Ɣ��x�w�����N�x
���E���w�S�W�╶�ɂƂ��Ċ��s���Ă����o�ŎЂ���̈˗������������낤���A�e�X�̕����ܑ咷�ҏ����̂����ȏ�̏�����|���̏����̖|����c���Ă��Ȃ������A�e�X�̕��̌o���ȂǁA�C�ɂȂ�Ƃ��낾�B
�l�����o���Ă���k�_�M�s�����͂��߁A���̒��S�̓h�X�g�G�t�X�L�[�ł͖����Ȃ�����A�h�X�g�G�t�X�L�[�ܑ̌咷�ҏ����̖|��ɂ����g�d���Ԃ�Ɍh�ӂ�\�������B�����I�ɌÂ��Ԃ�́A�������Ă���Ï��ŁA�܂��́A�ꕔ�A���ݎs�̒��̕����̓d�q�{�œǂ߂�̂ŁA������A���낢��ƎQ�l�ɂ����Ă��������B
�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[805] 2025/11/30/(Sun)21:19:11
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�w�����N�x�̈ʒu�t���̂��� |
| �{�� |
�@�@���NjL�X�V 25/12/03 20:30
�ܑ咷�҂̑n��̗���ɂ����鏬���w�����N�x�̈ʒu�t���ɂ��āA���t�[�m�b�܂ŁA�����̋C�t�����t���āA�����Ă݂܂����B
�@�@���@�����AI�̉́A�������B
�w�����N�x�̑n��̓��@��w�i�A�����������ߒ��A���̈ʒu�t���Ȃǂɂ��ẮA�܂��A�悭�킩��Ȃ��_������A����A����ɁA���낢��ƒm��A�l���Ă��������Ǝv���B
�@
�@�@[�u�k�А��E���w�S�W(1974�N�`1991�N��)
�@�@�@�̊�44�w�����N�x(�k�_�M�s��)]
�@�@�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[804] 2025/11/21/(Fri)20:23:32
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�Έ�M�m���w�h�X�g�G�t�X�L�[�Ɋw�ԁA�����@���x |
| �{�� |
�@�@���NjL�X�V 25/11/23 12:50
���̂��т̃y�[�W�̍X�V�ŃR�[�i�[�u���T�̖{�v�ɋ������{(�Z��Kindle�ł̓d�q�{)�ł����A
�@�Έ�M�m���w�h�X�g�G�t�X�L�[�Ɋw�ԁA�����@���x
���A����A�����ÁX�ɓǂ݂܂����B
�͂��ƂɁA�h�X�g�G�t�X�L�[�̐��U�̎�Ȏ��ՂɐG��A��N������u�𗧂ĕs�K�������₵���ނɂ��Ĕ����̂��ƕ��M�����ɑł����h�X�g�G�t�X�L�[�̂��̐����l���ƂƂ��Ă̐����̐��U����w�ׂ鐬���̖@�����܂Ƃ߂ċL���Ă��܂��B�����ɁA�s���h�X�g�G�t�X�L�[�_�ɂȂ��Ă��āA�ǂ݂�����������܂��B�������߂ł��B
�@�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[803] 2025/11/15/(Sat)16:18:56
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
���T�ɂ�����A���T�ŗ������Ă������� |
| �{�� |
�h�X�g�G�t�X�L�[�������������╶�͂̌��T�ɐG��ăh�X�g�G�t�X�L�[�̕��w��v�z�������ƒ�(����)�ɗ������Ă������Ƃ������ƂŁA���V�A��̊�{��╡�G�Ȋi�ω��Ȃǂ̕��@�����𒆐S�ɁA�܂��܂��K�����Ă���Ƃ͌����Ȃ����V�A��̕����ŋ߂��炽�߂ĊJ�n�����Ƃ���ł��B
�E���T�œǂݐi�߂Ă�����悤�ɂ��邱�ƁA
�E�M��̂Ԃ���Q�l�ɂ��A����ʁA�����A�`���̉ӏ��A���̂���ӏ�(�M��҂ɂ���Ė���Ă���ӏ��Ȃ�)�A�L�[���[�h�Ȃǂ��A���T�ɂ������Ă݂āA���V�A��̓Ǝ��̈Ӗ�������j���A���X���킩������܂��Ȃ���Ӗ�����e�𗝉����Ă�������
��ڎw���Ă��܂��B
�Ȃ��A���T�̑S�W(�i�E�J�őS�W�̂Ԃ�)�͏������Ă��Ďg���Ă��܂����A���T�̖{�����l�b�g��ʼn{���ł��邱��(������)�A�w�߂Ɣ��x�̖���ʂ̉ӏ��̌��T�{����I���Ζ�̌`�Ō�咍�t���ōڂ��Ă���{�����s����Ă��邱��(������)�́A���肪�����āA���肵�āA���p�����Ă�����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�C�ɂȂ邱�ƂƂ��āA���t�[�m�b�܂Őq�˂Ă݂��Ƃ���A�h�X�g�G�t�X�L�[���p���������̃��V�A��́A����̃��V�A��ƁA�Í����l�Ɏg����{��b�╶�@�ʂŁA�قڕς��͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B
����ɁA���V�A��̓�����X�������V�A�l��V�A�Љ�ɗ^���Ă���e���ɂ��ĕ����Ă݂��Ƃ���A���낢��Ƌ����[�����`�h������Ԃ��Ă��܂����B����Ɖ��������B
����A�����Ɛi�߂Ă������X�̃��V�A��̊w�K�ƌ��T�ɂ������Ƃ�ʂ��āA�C�t�������Ƃ�����A�����A���{�[�h�ɓ��e���Ă����\��ł��B
�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[802] 2025/11/09/(Sun)21:14:58
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�������ɁE�]����w�J���}�[�]�t�̌Z��x |
| �{�� |
�S�S���Ƃ��āA���̂U���Ɋ��P�E�Q�A�V���E�W���Ɋ��R�E�S��Kindle�łł����s���ꂽ�]����w�J���}�[�]�t�̌Z��x���D�]�̂悤���B(�X���ɓ������������ɂƂ��Ĉꊪ�{�ɂ���Kindle�ł��o�Ă���B)
������w�߂Ɣ��x�̖�̂悤�Ȏv�������r���Ȋ����̖��͂��܂茩���Ȃ����̂́A�w�߂Ɣ��x�Ɠ������h�X�g�G�t�X�L�[�̏������E�̕��͋C����肭�����o���Ă��邷���ꂽ��ł���B�ׂ�������t���Ă��邱�Ƃ��d��Ă��鏊��(�䂦��)���낤�B
�������A���A���̍]���ŁA�w�J���}�[�]�t�̌Z��x��ǂݕԂ��Ă���B
�@
�@�@�@
�@�@�@�@ |
| |
|
| |
[801] 2025/11/03/(Mon)20:42:19
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
���C�V���L�����݂̂���(�W) |
| �{�� |
�@�@���NjL�X�V 25/11/04 7:20
�w���s�x�̓��e�ŁA�ߔN�A�C�ɂȂ��Ă��āA�����ƁA�m�肽�����Ƃ́A��҃h�X�g�G�t�X�L�[���t�^���Ă��郀�C�V���L�����݂̐l�������B
�ނ́A�P�ɁA���Ԓm�炸�̂��l�D���A�s�K�Ȑl�ɑ������݂̏�̐[���l�Ƃ������l���E���i��\�����Ɏ����Ƃ̂ق��ɁA�쒆�̂������̌������悭���Ă����Ȃ�A���ʂɍl����M�O(�M�ʂ̂��Ƃ�)����(����܂œ��y�[�W�ł����Ύ��グ���u�ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����������̂��Ɓv(������)�Ȃ�)��Y�݂⊋���G�ɕ������閧�߂����l���̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���̂��Ƃ́A���C�V���L�����݂������̍�҃h�X�g�G�t�X�L�[�̏��Ȃ���ʕ��g���Ƃ����������������̂����m��Ȃ��B
�����ŁA���̂��т��A�ȏ�̂��Ƃ��A���t�[�m�b�܂ŕ����Ă݂��B
�@�@�@���@����Ɖ́A������
�������ɁA�`�h����́A������A����(��������)�A
�h�X�g�G�t�X�L�[�͌��݂�ʂ��āA�����ȑP�ƈ��������Љ�ł����ɐƎ�ł��邩�Ƃ�������N�Ɠ����ɁA���̏������䂦�̋�Y�⊋�����`���o���Ă���A��ʓI�ȗ��z���ł͂Ȃ��A���G�ȓ��ʂ����l�ԂƂ��ĕ`���Ă���ƌ�����ł��傤�B
�ȂǁA�s�������Ă���Ă��܂��B
���y�[�W�ł��܂��ۑ�ɂȂ��Ă��郀�C�V���L�����݂����������R�̖������������u���������v�̂��Ƃ��͂��߁A���C�V���L�����݂������Ă���l����Y�݂ȂǁA���コ��Ɋm�F���m���Ă��������B

[�\�A�f��u���s�v�̂P�V�[���B���C�V���L������
�@�ƃi�X�^�[�V���]�t�B���|���i�B]
�@�@�@ |
| |
|
| |
[800] 2025/10/31/(Fri)18:07:24
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̂�����Ă���_(�T) |
| �{�� |
�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�́A�W�听�Ƃ��āA�h�X�g�G�t�X�L�[�̔ӔN�̎v����l�����l�ߍ��܂�Ïk���Ă���Ƃ����_�ł��炵�����A�X�g�[���[�̂��Ƃ͂Ƃ������Ƃ��āA�o�ꂵ�Ă���l�����悭�`����Ă���Ƃ������Ƃ�������Ă���_���ƍŋ߂��炽�߂Ďv���B
�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ɓo�ꂷ��l���͕ς�����l����������ǁA�w�J���Z��x�ł��A�O�Z��╃�t���[�h�����l�̏����͂������A�e���܂ł��A���̐[������������ă��j�[�N�ɐ▭�ɕ`����Ă���B�X�����W���R�t��z�t���R�[���@�v�l�Ȃǂ̃L�������ʔ����Ƃ��炽�߂Ďv���B
�o��l���������ɏ�肭�`����A�������Ă��邩�Ƃ������Ƃ������̂��̂��̑厖�Ȉ���ƌ����邾�낤�B
�@�@�@�@
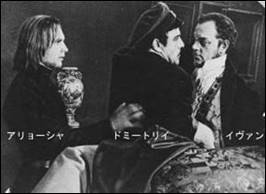
�@�@�@ |
| |
|
| |
[799] 2025/10/25/(Sat)14:59:15
| ���O |
Seigo
|
�^�C�g�� |
�h�X�g�G�t�X�L�[�Ɋւ���e���� |
| �{�� |
�h�X�g�G�t�X�L�[�Ɋւ��āA
�@�h�X�g�G�t�X�L�[�̐l�Ԋ�
�A�h�X�g�G�t�X�L�[�̎��R�ς͂ǂ����痈���̂�
�B�h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ�����u�_�v�̂���
�C�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ɂ������ȃe�[�}
���A���������āA���t�[�m�b�܂Ŏ��₵�Ă݂܂����B
����Ɖ́A
������
�@�@
�@�A
�@�B
�@�C
�`�h������́A�����̒ʂ�A�������肵����������Ă��܂��B
�l�Ԋςɂ��ẮA�����ƁA��Ȃ��̂������Ăق��������Ǝv���B
�@�@�@���@����������܂ŋ������Ԃ�
�h�X�g�G�t�X�L�[�̐l�Ԋςɂ��ẮA����������Ă��������B
�h�X�g�G�t�X�L�[�̎��R�_�ɂ��ẮA
�`�h���́A
�h�X�g�G�t�X�L�[�̎��R�_�̓����́A�P�Ȃ�O�I����̉���ł͂Ȃ��A�u���R�̏d�ׁv��������ӔC�ƁA���҂ւ̈��ɂ�鎩�Ȑ������܂ޓ_�ɂ���܂��B�ނ͖������̎��R���K�R�I�Ɏ��Ȕj��Ɏ��邱�Ƃ��w����x�̃L���[���t�Ȃǂ̐l����ʂ��ĕ`���A�^�̎��R�̓L���X�g���I�Ȉ��ƌ�����ʂ��Ď�������Ƃ����Ǝ��̎��_�������Ă��܂��B
�Ƃ����w�E�́A�s�����̂�����A�l���������܂��B
�@�@�@ |
| |
|
 �@�@�@�@
�@�@�@�@